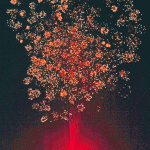「大竹」という地名を聞いて、大竹市全体を想像する人もいるかもしれませんが、1954年(昭和29年)に市制が施行されて「大竹市」になる以前の旧大竹村の地域は、現在の「元町」、「白石」、「本町」、江戸時代に埋め立てられた「新町」、「小島(栄町)」にあたり、これらの地域を現在でも「大竹」と呼んでいます。
大竹は、安芸と周防の国境にあるため、日本史の歩みの中に、大きく関わりを持った地域です。
西暦600年以前を古墳時代と言われますが、広島県下の市町で「古墳」がない町は大竹市だけと言われています。
それは、山林・平野がなく、小瀬川の自然が砂を運び、河川が陸地化となったとこが唯一生活を支えると言う生活環境で、この頃の大竹村は、「大谷(おおたけ)とて 岸高き山河 流れ出で見ゆ」とうたわれているように、山と海に挟まれ、住む条件は決して整っていたとは言えませんでした。こうした所には豪族、豪農が存在しないのが、「古墳」のない理由と言えます。
いつの時代かわかりませんが、大竹村に人が住み始めたのは「平原7軒、浴(えき)3軒」と語り継がれています。
平原は、現在の白石1丁目の辺りと言われています。また、浴は、現在の元町四丁目薬師寺西側の谷間とされています。記述では、西暦587年9月19日、弥ケ迫(いやがさこ)に氏神が創建されたとあり、この頃、集落が山裾に、海の幸を求めて住むようになったと考えられます。
そして、推古天皇即位の年、西暦593年、伊都岐嶋姫命と佐伯鞍職(さいきくらもと)との関わりを示す、厳島神社創建伝説が伝えられています。
大竹村の村人となった、佐伯鞍職が大和の宮中から流刑となり、瀬戸内海を西に向い辿り着いた薬師寺・疫神社辺りまでは、大きく入り組んだ瀬戸の入江であったといわれ、ここを「沙々羅浜」と呼び、川の向こう岸を関ヶ浜と呼んでいました(現在も呼ばれています)。
厳島神社が大竹村の人により創建されたという伝説は、大竹市民にとって誇りであり、大切に語り継いでいきたいものです。
大竹村の地名も、色々な説が乱れ飛び、「横竹」と書いておおたけという説、太古の昔、弥栄ダム辺りが分水嶺で、大竹川に流れる辺りに大きな滝があったとも説や竹が多いから大竹という説もあります。
しかし、確かな説明をすることのできる言い伝えもなく、どれをとっても納得の行く説明にはなりません。
しかし、天平6年(734年)、続日本書紀第十一巻に「大竹川をもって安芸・周防の国境とする」とあるように、「大竹」という地名は、古くから使われていたようです。
現在の和木町は、あまり国境が統制上ハッキリしていない時代、大竹村の「脇」にある小さな集落であったことから呼ばれるようになり、後に「和木」と字が変わったと言われています。
中世の毛利氏の時代まで、小瀬川を挟んでの争いはなく、大竹村の人は、関ヶ浜や和木の山林に入り、落ち葉や草木を持ち帰り、田畑の肥料としていました。また、関ヶ浜の村人は、大竹村の干潟に貝掘など、魚介類を求めて自由に行き来していました。
ところが、関ヶ原の戦いの後、毛利家は萩に追いやられ、小瀬川を挟んで所領が分断されることになり、双方の村人たちは行き来を遮断され、村人たちの感情も一変しました。
江戸時代に入ると、小瀬川周辺の境界論争があり、大竹村の人が関ヶ浜に行くと追い返される事態になり、その対抗策として、大竹村の磯に来る和木・瀬田・そして関ヶ浜の村人に手厳しく貝掘りを妨害するなど、険悪な状況は200年も続きました。
享和元年(1801年)になって、ようやく両藩が合意し、青木堤防の所で川の中央に杭を打ち、芸防の境界を定め、それ以後は紛争はなくなり、沖新開(1804年)中新開(1803年)、郷水新開(1804年)と新開開発が急速に進み、天保3年(1832年)小島新開が完成しました。
このように大竹村の発展は現在の元町四丁目辺りから下流に向って徐々に開け、新町、栄町あたりは江戸時代に開埋め立てられた非常に歴史の浅い地域となっています。
そして、町の繁華街も時代とともに移り変わり、かつては中市(元町二丁目)と言われたように元町周辺が中心的な賑わいを見せていましたが、本通り(本町一丁目・二丁目)、そして大竹駅前通り、栄町といったように変化しています。
明治に入ると海外移民として多くの村人が新天地を目指し、また、昭和10年代に入ると小島新開は軍事的な拠点施設が立地し、終戦後は、海外からの引揚げ港として、一年余に42万人の軍人や国民が、祖国日本への一歩を大竹で踏みしめました。
そして戦後、日本の経済成長の担い手として企業誘致に成功し、日本で初めての石油コンビナートである岩国・大竹臨海工業地帯として発展しました。